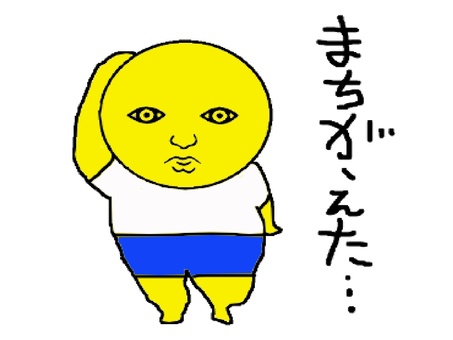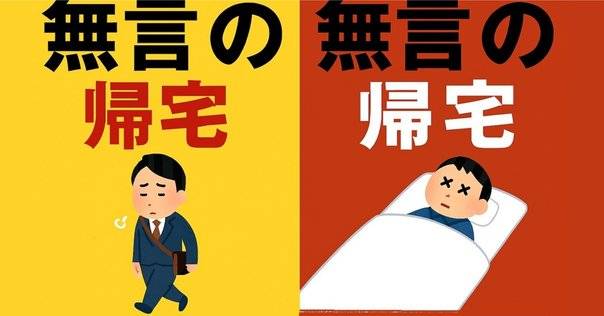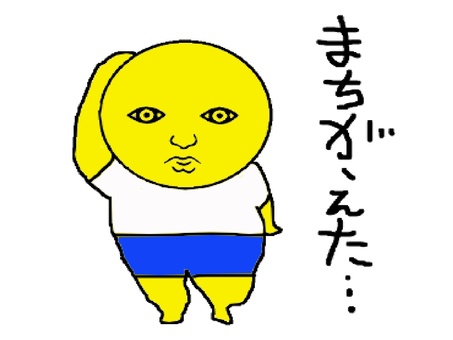先日、よく見るSNS上で、
『無言の帰宅』についてのコメントが盛り上がっていた。
「行方不明だった夫が、『無言の帰宅』をしました。」
に対して、
「見つかってよかったですね。でも帰って来たのなら、ちゃんと ”ただいま” を言って欲しいですよね~」
とか、
「心配かけてゴメン、とかはなかったんですか?」
など、的外れなコメントをする人が一定数いるらしい。
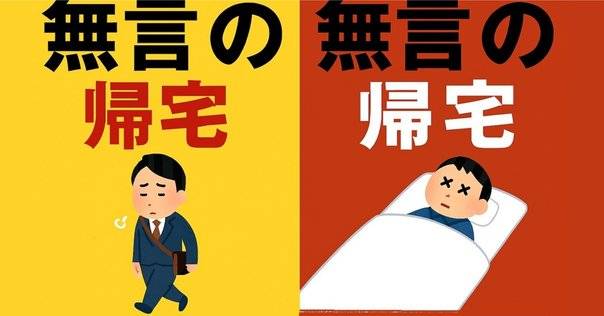
ちなみに夢現塾生諸君、この『無言の帰宅』の意味は分かったかな?
六名校5年生H・Y君はその意味は知らなかったけれど、なぜかヒントなしで当てました!
正解は、「死んでしまった」という意味で、「死」を直接言わないための「婉曲(えんきょく)」表現です。
(「わんきょく」って読んだ人、残念!!)
※婉曲(えんきょく)・・・遠まわしに伝え、直接的な表現をしないこと。
愛するペットが亡くなった時に、
『虹の橋を渡った・・』というのも同じく婉曲表現だ。
このように「死」を直接的に言わないための言葉はいくつもあり、
『鬼籍(きせき)に入る』や仏教用語の、
『荼毘(だび)に付す』などもそうだ。
だがこれに対し、この言葉を知らない人を責めたり笑ったりするのは、なんだかちょっと違う気がする。
「大人ならば知ってるのが常識」と言ってしまうのは簡単だが、「一般常識」っていったいどこまでなのかは、割と曖昧なものだ。
だから僕は ”知らない人を責める人たち” には賛同できなかった。
しかし問題はこの後だ。
「そんな言葉、聞いたことがない!」
「もっと分かりやすく書け!」
と、知らなかった人が逆ギレしている点には、ちょっと疑問に思った。
知らないことは「知らなかった」と認めれば済むだけの話なのに、とにかく自己正当化をする人が一定数いるし、モンクレ同様にそういう人に限って声が大きい(笑)
自分の間違いを認められない人、謝れない人が増えているのだろうか?
それともSNSのおかげでこのような人が可視化されただけなのか?
後者であることを願ってやまない。
さて、夢現塾生諸君。
「はぁ?知らんし」や
、「でも」・「だって」が口ぐせになってる人、いませんか?(笑)
自分の間違いを認めることって、とても勇気がいることだけど、
「ゴメンなさい」や
「ありがとう」が言えるって、人間としてとても大切なことだよ。